寒さが厳しくなる冬は、甘みが増して栄養価の高い「冬野菜」のベストシーズン。
鍋料理やスープなど、体を芯から温めるレシピに欠かせない食材ばかりです。
この記事では、冬におすすめの旬の野菜をランキング形式で10品厳選してご紹介!
それぞれの野菜の特徴や栄養、調理のコツもまとめています。
冬野菜を美味しく食べて、健康で温かい冬を過ごしましょう!
冬野菜の魅力とは?

冬に旬を迎える野菜には、次のような特徴があります。
甘みが増して美味しくなる
気温が0度に下がってしまうと野菜内の水分が凍ってしまいますが、そうならないように野菜自身が糖度を上げることによって凍結しにくくします。
この作用によって冬の野菜は甘みが増します。
また、この作用を利用し栽培されたのがちぢみほうれん草です。
わざと霜に触れさせることで葉がちぢみ糖度が高くなります。
積雪の下で保存する「越冬キャベツ」「雪下人参」もこの作用を利用した冬の野菜で甘みが増します。
虫が少なく見た目もきれい
冬は気温が低いため畑での虫の発生が少なく虫食いになる野菜が少ないです。
そのため冬野菜の見た目がきれいで料理もきれいに仕上げることができます。
畑で野菜の中に入り込んでくる虫も少ないため安心して食べることができます。
冬野菜は見た目がきれいなものが多いです。
体を内側から温める栄養たっぷり
冬野菜は、ビタミンEとビタミンCが多く含まれています。
ビタミンEには血行促進作用、ビタミンCには鉄分吸収促進作用があり、この働きによって体が温まります。
かぶ、人参、白ねぎ、小松菜などは冷えを取り除き体を温める野菜です。
白菜や大根は水分が多く生で食べると体を冷やしてしまいますが、加熱調理することによって体を温めてくれます。
冬はおでんや鍋など加熱調理した料理を作る機会が多いため調理方法を工夫することによって体を温めてくれます。
【ランキング】冬が旬のおすすめ野菜10選

ここからは、冬に旬を迎えるおすすめ野菜をランキング形式でご紹介します!
第10位:かぶ|柔らかくて上品な甘さが魅力
かぶは、多くの品種があり大きいものから小さいもの、色も赤、白、黄、紫など地域によって様々です。
煮物、漬物、焼き物など様々な調理方法があります。
皮も食べられますが大きいものは厚めに皮をむいた方が食感が良くなります。
茹でる際かぶは火の通りが早いので茹で過ぎに注意が必要です。
赤かぶは、漬物や酢の物、サラダなど生で食べる方が鮮やかな色のまま食べられます。
第9位:春菊|独特の香りで食欲アップ
春菊は春に黄色の花を咲かせ葉の形が菊に似ているので「春菊」と呼ばれています。
関西では、「キクナ」とも呼ばれています。
特有の香りと風味を持ち、葉の部分はサラダに茎はおひたしやみそ汁の具材として使用するのがおすすめです。
第8位:人参|栄養価トップクラスの万能野菜
人参は、βカロテンがずば抜けて多い野菜です。
人参1本の半分ほどで1日に必要なβカロテンの量が取れ免疫力を高めてくれます。
人参が苦手な子供が多かったですが、今では人参特有のにおいや風味を抑えた品種が増え、好きな野菜として知られるようになりました。
カレーやシチュー、煮物、サラダなど様々な料理に使える野菜です。
第7位:小松菜|鉄分とカルシウムが豊富
小松菜は、お吸い物、漬物、炒め物など多くの調理方法で使用することができます。
一年中、栽培されていますが、冬の時期は寒さで甘みが増します。
カルシウムを多く含んでいるので骨粗しょう症予防になる緑黄色野菜です。
第6位:キャベツ|冬は甘みと旨味が段違い!
キャベツは、調理用途が広くたくさん作られている野菜です。
春キャベツは巻きが緩く葉が柔らかいので生食に向いていますが、冬キャベツは葉がしっかりと巻いていて甘みがあるのが特徴です。
キャベツには、ビタミンUが含まれていて胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの胃腸障害を予防、改善する働きがあります。
冬キャベツは、煮崩れしにくく煮込み料理に適しています。
第5位:ほうれん草|冬にこそ甘くなる栄養野菜
ほうれん草は、鉄分、ビタミンC、カロテン、ビタミンB1、ビタミンB2、葉酸などが多く含まれ栄養価の高い野菜です。
おひたし、炒めもの、茹でたりとおいしいほうれん草を料理の一品に加えてみましょう。
最近は、寒さから身を守るため糖度が高くなるちぢみほうれん草の栽培も盛んです。
第4位:ブロッコリー|栄養満点!彩りと食感も◎
ブロッコリーは、アブラナ科の緑黄色野菜で花蕾(からい)と呼ばれるつぼみの部分を主に食用として食べます。
栄養素が豊富でビタミンC、葉酸、ビタミンE、ビタミンK、カリウム、食物繊維などが豊富に含まれています。
ビタミン類の流出を防ぐため茹でずに電子レンジで加熱するのがおすすめです。
第3位:白ねぎ|加熱で甘みが際立つ冬の主役
白ねぎは、土を寄せて根元に日が当たらないようにして白い部分が多くなるように生育させます。
火を通すと甘みがでるので鍋や煮込み料理、串焼きに使用されています。
また、細かく刻んで薬味にも使用できます。
保存するときは、横に寝かせておくと白ねぎが上にいこうとする力が作用し曲がってしまうので、立てて保存しておくと良いです。
第2位:白菜|冬の鍋に欠かせない主役級野菜
白菜は大きくなるにつれて白い部分が太く伸びるため「白菜」と呼ばれています。
味はくせがなく、やや甘い味が特徴です。
冬は寒さにより葉の糖分が増しおいしくなります。
冬の鍋ものには、なくてはならない野菜です。
他にも浅漬け、サラダ、スープ、炒め物など様々な料理に活用できます。
第1位:大根|甘くてみずみずしい冬の王様
一般的に出回っている約90%のものは「青首大根」といわれる種類になります。
冬の大根は、甘みがあってみずみずしく柔らかいのが特徴です。
先端部は、辛みが強いと言われていますが冬の大根は先端部分でも甘く食べることができます。
煮物にしても良いし、サラダや漬け物などでも甘くみずみずしい大根が味わえます。
冬野菜をもっと美味しく食べるコツ

冬野菜をもっと美味しく食べるコツを紹介します。
加熱調理で甘みを引き出す
冬野菜は寒さにより糖分が増し、甘みが凝縮されています。
生で食べるのも良いですが、加熱することでさらにその甘みが引き立ちます。
特に大根や白菜、キャベツは煮物や鍋で加熱することで、甘みが強くなり、柔らかくなります。
炒め物やスープにすると、甘さとともに野菜の旨味も増し、さらに美味しくいただけます。
季節の野菜を味わうためには、加熱調理を活用することがポイントです。
調理法を工夫して栄養を逃さない
冬野菜は栄養満点ですが、調理法によって栄養素が流れ出てしまうことも。
特にビタミンCや食物繊維は熱に弱いので、電子レンジで加熱するのがおすすめです。
茹でる場合も短時間でさっと火を通すと栄養を逃しにくくなります。
また、スープや煮物にして、野菜の栄養がスープに溶け出すようにするのも効率的な方法です。
冬野菜を栄養価たっぷりに楽しむには、調理時間を短くする工夫が大切です。
組み合わせで味のバランスを整える
冬野菜はそれぞれに個性があり、調味料との相性が大切です。
例えば、甘みの強い大根や白菜は、味噌や醤油といった濃い味付けと相性が抜群です。
反対に、苦味や香りが強い春菊やほうれん草は、甘みのある食材や酸味の効いたドレッシングと合わせると、味のバランスが整い、食べやすくなります。
様々な野菜を組み合わせて、風味の相乗効果を楽しみましょう。
よくある質問(FAQ)

Q. 冬野菜の保存方法は?
A. 白菜やキャベツは新聞紙に包んで冷暗所へ。ブロッコリーやほうれん草は茹でて冷凍保存もOKです。
Q. 生で食べると体が冷えませんか?
A. 白菜や大根など一部の野菜は、生で食べると体を冷やすことがあります。加熱調理がおすすめです。
冬野菜で体も心も温まる!新鮮な野菜は食べチョクで手軽にお取り寄せ
冬野菜は、寒い季節にぴったりの栄養満点な食材です。
甘みが増し、体を温めてくれる野菜を使った料理は、心も体もほっと温まります。
もし、手軽に新鮮な冬野菜を手に入れたいなら、「食べチョク」がおすすめ!
全国の農家から直送された新鮮で美味しい野菜が自宅に届くので、忙しい毎日でも簡単に旬の味を楽しめます。
今すぐ食べチョクで、お取り寄せしてみましょう!




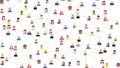
コメント