ここ数年、日本では食料品や日用品、電気代、家電製品など生活に欠かせないものの値上げが相次いでいます。
給料が思うように上がらない中で物価だけが上がると、家計のやりくりはますます厳しくなりますよね。
一人暮らしでも家族持ちでも、出費が増えるなかで「どうやって節約すればいいのか」と悩む人は多いでしょう。
本記事では、日本の物価が上がる原因をわかりやすく解説し、さらに今日から実践できる節約のコツ10選を紹介します。
物価が上がっているもの
まずは、実際に値上げされている商品やサービスを確認しましょう。
日用品

- ティッシュペーパー
- トイレットペーパー
食料品
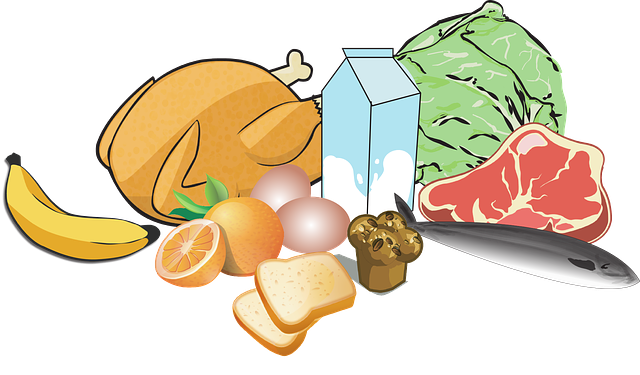
- 食用油
- 揚げ物
- 弁当
- 飲料類
- 調味料
- 菓子類
- 麺
- パン
- ソーセージ・ハム
- 冷凍食品
家電製品

- 冷蔵庫
- エアコン
- 炊飯器
- 乾燥機
- プリンター
- カメラ
- ゲーム機
- 中古自動車
公共料金・交通費
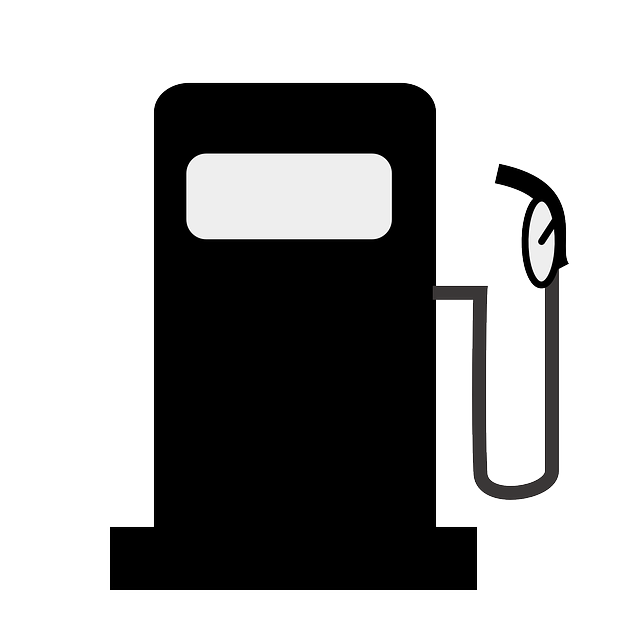
- 電気・ガス
- ガソリン代
- 飛行機・特急列車などの交通機関
日本の物価が上がる原因

日本の物価が上がる原因を紹介します。
原材料の価格上昇
物価が上昇する一因として、原材料の価格上昇が挙げられます。
工業製品の製造や農産物の生産に必要な原材料の価格が上昇すると、それらを使用する製品や食料品の価格も上昇します。
石油や穀物などの主要な原材料の価格上昇は、広範な製品やサービスの価格に影響を与え、メーカーやスーパーなどで値上げがされています。
労働コストの上昇
企業で働く従業員の賃金や労働条件の改善により、企業の生産コストが上昇すると、製品やサービスの価格に転嫁され物価が上昇します。
企業も利益率を維持しなければならないため価格を上昇させます。
労働の最低賃金も上昇の傾向にあります。
円安の影響
輸入品の価格は為替レートに大きく影響されます。
国内通貨の価値が低下すると、輸入品の価格が上昇し、それが物価全体の上昇につながります。
特にエネルギーや食料品などの輸入品は、為替レートの変動に大きな影響を受け、円安になると物価全体に影響を与えています。
需要と供給のバランス崩壊
需要と供給のバランスが崩れると、物価が変動します。
需要が供給を上回ると、物価が上昇し、需要が供給を下回ると、物価が下がります。
需要の増加は、景気の好転や人口増加など様々な要因によって引き起こされます。
一方、供給の減少は、天候不順や自然災害などの要因があります。
自然災害
大規模な自然災害には、洪水、台風、地震などがあります。
自然災害により生産設備が壊れたり、生産ラインが中断したりすると生産することができず供給が停止してしまいます。
特に、農作物や原材料の供給に大きな影響を与える自然災害は、商品の価格を上昇させてしまいます。
また、自然災害が物流や輸送に影響を与える場合、製品の供給が減少し、需要が高まると価格が上昇します。
政治的不安定
政治的な不安定や紛争が発生すると、投資や生産が減少し、経済が不安定になります。
このような状況下では、企業はリスクが高まるため、価格を上げて利益を確保しようとする傾向があります。
また、政治的な不安定は通貨価値の低下や輸送インフラの損傷などの影響をもたらし、これらが物価上昇になります。
物価高騰に負けない!節約のコツ10選

物価が上がり出費が増えるので節約するコツ10選を紹介します。
価格が安定している食材を選ぶ
たくさんの食料品が値上がりしていますが、比較的物価上昇の影響を受けていない食材を選ぶようにしましょう。
鶏胸肉、豚こま肉、ひき肉などの「肉類」、もやし、きのこ類などの「野菜」、「卵」、「大豆」製品などを選びましょう。
野菜は、今後、肥料の高騰により値上がりしそうです。
また、野菜を家庭菜園で作ることも節約につながります。
外食を減らして自炊中心に
外食は値上げ傾向にあるので、今までと同じように外食を利用すると出費が増えます。
誕生日やお祝いごとなど特別な日に絞ることで節約ができます。
ファーストフードでも一人1,000円くらい、ファミリーレストランでも一人1,000円~2,000円くらいかかります。
PB商品・セール品・見切り品を活用
PB商品も値上げはされますが、メーカーの商品と比べると値上がり幅は小さいです。
どうしてもこのメーカーの商品がほしいというわけではない場合は、PB商品を買うのがおすすめです。
また、その日限りや数量限定となっているセール品も狙い目です。
見切り品であれば安くなっていますのでチェックしてみましょう。
クーポン・割引券を使う
よく利用するスーパーやドラッグストアのアプリの会員登録をすればお得な情報やクーポンが配布されることがあります。
また、LINEのお友達登録をすることで割引券が入手できることもあります。
よく利用するスーパーやドラッグストアを上手に活用して節約してみましょう。
まとめ買いで単価を下げる
コストコやサムズクラブなどの倉庫型店舗で大量にまとめ買いをすることで1個あたりの値段が下がります。
また、買い物に行く回数を減らせるのでガソリン代節約にもなります。
但し、食品が傷んだりしてしまっては無駄になるので、必要以上のまとめ買いには気をつけましょう。
旬の食材を取り入れる
野菜や果物には旬の時期があります。
旬な時期であれば多くの量が収穫されるので、値段が少し安くなるうえに旬で味が美味しい時期であるというメリットもあります。
ぜひ、季節の野菜や果物を生かした料理を作ってみてください。
台所を整理して無駄を防ぐ
台所を整理することによって、どの食材があるのか分かるのでスーパーで不要なものを買うことがなくなります。
傷みやすい食材をすぐに冷蔵庫に片付けたり、古い食材を優先的に使用するように心掛ければ不要に食材を廃棄することも減るでしょう。
整理整頓をしておけば、食材の在庫が見えるようになり管理しやすくなります。
電気代を節約する
光熱費を抑えるために節約することも可能です。
冷蔵庫に食品を詰めすぎないようにしたり、エアコンのフィルターを掃除したりすることも電気代の節約になります。
また、照明や家電の電源をこまめに切るように心掛けましょう。
長年使用してない家電製品は、コンセントを抜いておきましょう。
訳あり食品を購入する
食材には、形や傷が多いからといって普段は廃棄してしまう食品があります。
その訳あり品をネットなどで安く購入することができます。
形が悪かったり、傷があっても味は同じです。
また、賞味期限の近い食品は、値段が割引きになっているものもあるので訳あり品を使用する方法もあります。
冷凍保存をフル活用する
安く売っているものを大量に買い、冷凍保存することによって食材を長持ちさせることができます。
キャベツ、トマト、ほうれん草などの野菜は冷凍保存可能です。
カットしておいたり、味付けして冷凍しておけば時短にもなります。
生活費を賢く節約して、ポイントも貯めよう!
日本の物価上昇で家計の負担が増える中、今日からできる節約術を取り入れることが大切です。
食材の選び方や外食の減らし方、冷凍保存やクーポン活用など、日常で実践できる工夫を重ねるだけで出費を抑えられます。
さらに、節約をもっと効率よく進めたい方には「ポイントサイトの活用」がおすすめです。
高還元率ポイントサイト《ハピタス》なら、無料会員登録するだけで買い物やサービス利用でポイントが貯まり、現金やギフトに交換できます。
節約術と併用すれば、日々の生活費をさらにお得にすることが可能です。




