社員から「会社を辞めたい」と相談されたとき、どう対応すれば良いか悩んでいませんか?
特に優秀な人材の退職は、組織にとって大きな損失になります。
しかし、無理な引き止めや間違った対応は、かえって逆効果になることも。
本記事では、会社を辞めたいと考える社員の退職の前兆から引き止める方法10選、NG対応、円満な送り出し方、原因改善のヒントまで、網羅的に解説します。
会社を辞めたい人を引き止めるのが難しい理由

社員が退職を考える背景には、さまざまな事情があります。
引き止めが難しいとされる主な理由は以下のとおりです。
覚悟を持って決断している
会社を辞めるという決断をすることは大きな出来事です。
簡単に考えて決断するものではなく、長い期間、悩んだり考えたりして決めたことです。
覚悟を持って決断したことを覆すのはたいへんな労力がいるでしょう。
価値観や目標の不一致
従業員が会社のビジョンや価値観と自分の考え方が合わないと感じた場合、引き止めることが難しいです。
また、個人のキャリア目標や人生観が組織の方向性とズレていると、「このまま働き続ける意味がない」と考えるようになり、会社に残る理由が薄れてしまいます。
個々の目標や価値観が一致しない限り、引き止めは難しいです。
ライフステージの変化
結婚、出産、家族の状況など従業員のライフステージが変化すると、働き方や働く場所に対する要望も変化します。
このような変化が大きい場合、引き止めが難しいことがあります。
仕事とプライベートのバランスは大切です。
すでに次の準備を進めている
新しい挑戦や成長の機会があると感じると、従業員は転職を選ぶことがあります。
会社を辞めると決めた人はすでに次にやりたいことに向けて準備していることもあります。
気持ちがすでに切り替わり、引き止めても留まる可能性は低いでしょう。
次に動き出す前に対処しなければなりません。
改善の余地がないと感じている
仕事を辞める人は長い期間、我慢をしてきて決断したことなので、会社に改善の期待はしていません。
改善を求めてもそこに費やす時間と労力がたいへんなため辞めた方が楽という考えになってしまっています。
会社が改善するように努めると思い留まる可能性はあります。
退職を考えている社員の前兆サインとは?
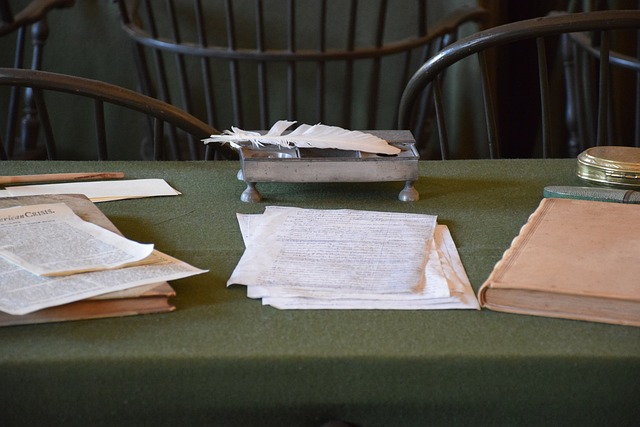
以下のような行動・態度が見られたら要注意です。
- 明らかにモチベーションが下がっている
- 遅刻や欠勤が増えている
- 雑談やコミュニケーションを避けるようになる
- 急に有給休暇の取得が増える
- プライベートの相談をしなくなる
- 社外の活動(資格取得、副業など)に力を入れ始めた
早い段階で気づくことが、引き止め成功のカギになります。
会社を辞めたい人を引き止める方法10選!

退職の意向を持つ社員に対しては、相手の立場に立ちつつ、具体的な改善策を提示することが重要です。
相手に寄り添う姿勢を持つ
会社を辞めたいと相談されたら、相手の気持ちを考えて相手に寄り添うようにしましょう。
議論や反論はせず、相手の話を一度全て聞いてみて受け入れる姿勢を持つことが大切です。
相手が話しやすい状況を作り、目を見てしっかり話を聞き、頷いて理解してあげるようにします。
また、周囲の目が気にならないように部屋を替えるなど配慮しましょう。
本音を引き出す
会社を辞めたい人が会社を辞めるときに本音を言う人は少ないでしょう。
会社や人間関係への不満が理由の場合は言いにくいので「他にやりたい仕事があるので」とか「健康上の理由で」「家庭の事情で」など建前で話をしてきます。
会社を辞めたい人が本当の理由を言ってくれるように努めなければなりません。
問題を解決するためには本音を言ってもらわなくては解決できません。
解決策を一緒に考える
相手が持っている不満や不安を聞いたなら一緒に問題を解決しようという姿勢が大切です。
人間関係が理由であれば部署移動や配置転換を考えたり、解決できそうな場合は行動に移しましょう。
相手の持っている不満や不安を解決しない限りは気持ちは変わらないでしょう。
その後、どういう仕事をやっていきたいか、会社として必要な人材であることを伝えると仕事のモチベーションも回復します。
定期的なコミュニケーションをとる
相手の不満や不安を聞き、理解することが大切です。
コミュニケーションを通じて問題点を明らかにし、改善のための提案を求めましょう。
従業員の不満や懸念事項を理解するために、オープンな対話をしなければなりません。
一対一の面談やフィードバックセッションを通じて、会社を辞めたい人が感じている課題や改善すべき点を明らかにしましょう。
キャリアの展望を提案する
社員が将来に不安を感じている場合は、「この会社でどう成長できるか」を具体的に示すことが大切です。
本人の得意なことや興味のある分野をもとに、キャリアの道筋を一緒に考えましょう。
役職のステップアップや新しい仕事への挑戦など、前向きな提案があると「ここでもう少し頑張ってみよう」と思えるようになります。
キャリアの展望が見えると、安心感ややる気につながります。
報酬・福利厚生の見直し
給与や福利厚生に不満があると、他の職場へ気持ちが向きやすくなります。
市場の相場や同業他社と比較し、適切な報酬や制度が整っているか見直すことが重要です。
昇給や手当の改善、柔軟な働き方、休暇制度の充実など、具体的な改善策を提示することで、社員の不満を軽減し、離職の防止につながります。
公平で納得感のある待遇は、安心して働ける職場づくりの基本です。
メンタル面のサポート体制を整える
従業員の心の健康を支えるメンタルサポートは、退職防止に効果的です。
相談窓口の設置や専門カウンセラーの活用、ストレスチェックの実施など、安心して話せる環境を整えましょう。
また、働きやすい職場づくりや適度な休息の推奨も大切です。
メンタル面のサポートが充実していることで、社員の不安や負担が軽減され、長く働き続ける意欲が高まります。
感謝の気持ちを伝える
相手の仕事への貢献や努力に対して感謝の意を表明し、従業員の存在が会社にとってどれほど重要かを伝えます。
感謝の表明は、従業員のモチベーションの向上になります。
しっかりと相手の仕事を評価し、それに応じた感謝の気持ちを伝えましょう。
社内イベントやチーム活動の充実
社内イベントやチーム活動を充実させることで、社員同士の絆が深まり、職場の居心地が良くなります。
仕事以外の場で交流を持つことで、コミュニケーションが活発になり、協力しやすい環境が生まれます。
これにより、社員の満足度や帰属意識が向上し、離職率の低下にもつながります。
楽しいイベントは社員のモチベーションアップにも効果的です。
働きやすい環境の整備
働きやすい環境を整えることは、社員の定着率向上に直結します。
柔軟な勤務時間やリモートワークの導入、快適なオフィス環境の提供など、個々のニーズに応じたサポートが重要です。
また、過重労働の防止や適切な休暇取得の推進も大切です。
こうした取り組みで社員のストレスが軽減され、仕事に集中しやすくなり、長く働き続ける意欲が高まります。
会社を辞める人に絶対やってはいけないNG対応

以下のような対応は、社員の信頼を失い、逆に辞める決意を強めてしまう可能性があります。
会社都合ばかりを押し付ける
仕事を辞めたいと言われて「今は忙しい時期だから辞めてもらうと困るな」とか「人手不足だからもう少し頑張って」など本人の意思が関係なく会社の都合で話をしてはいけません。
誰でもよくて会社に必要な人材ではないと思われ、やりがいが持てず退職してしまいます。
相手にしっかり向き合って話をしましょう。
その場しのぎの約束をする
仕事を辞めてほしくないからといってその場しのぎで話をしないようにしましょう。
できもしないのに「給与を上げるから」とか「人事部に異動を投げかけてみる」などその場しのぎで話をして改善できない場合、信頼が失われ結局、仕事を辞めてしまうことになります。
相手に寄り添いしっかり話を聞く時間を作りましょう。
退職の話を他の社員に広める
仕事を辞めたいと相談されて解決できる方法があるのに他の社員に広く伝わってしまうと逆に会社に居づらくなり、退社をうながしてしまうことになります。
あまり他の人には知られたくないことでもあるので、広く話が回らないように配慮しましょう。
信頼関係が築けないと解決も困難になり、退社を引き止めることもできなくなってしまいます。
強引に説得する
退職の意思を示した社員に対し、何度も面談を繰り返したり、「とにかく残ってくれ」と感情に訴えるなど、強引に説得するのは逆効果です。
本人が十分に考え抜いて出した結論であることが多く、無理に引き止めようとすると、かえって不信感やストレスを与えてしまいます。
結果として、退職の意思がさらに固まることにもなりかねません。
説得ではなく、冷静に対話を重ね、相手の気持ちを尊重する姿勢が大切です。
非難・批判をする
退職を申し出た社員に対して「無責任だ」「甘えている」などと非難や批判をすることは、絶対に避けるべきNG対応です。
こうした言葉は相手の人格や判断を否定することになり、強い不快感や不信感を与えてしまいます。
また、職場の雰囲気を悪化させ、他の社員にも悪影響を及ぼす可能性があります。
引き止める際は、批判ではなく理解を示し、前向きな対話を心がけることが、信頼関係の維持につながります。
感情的になって怒る、責める
退職の話を聞いて感情的になり、「なんで辞めるんだ!」「裏切りだ」などと怒ったり責めたりするのは絶対に避けるべき対応です。
本人は長い時間をかけて悩み、決断を下している場合が多く、その気持ちを否定されると強いストレスや不信感を抱きます。
感情をぶつけても状況は改善せず、関係が悪化するだけです。
冷静に話を聞き、相手の立場や気持ちに配慮した対応をすることが、円満な関係維持につながります。
他の社員と比較する
「○○さんは辞めずに頑張っているのに」「あなたのほうが優秀なのに辞めるの?」など、他の社員と比較して引き止めるのは逆効果です。
比較されることでプレッシャーや不快感を抱き、自分が正当に評価されていないと感じる原因にもなります。
社員一人ひとりには異なる事情や価値観があるため、個別に向き合う姿勢が大切です。
他人と比べるのではなく、本人の考えや気持ちにしっかり耳を傾ける対応を心がけましょう。
秘密裏に特別待遇を提示する
退職を引き止めるために、他の社員には内緒で「特別に昇給する」「役職を与える」などの待遇を提示するのはNGです。
このような対応は社内の公平性を損ない、後に発覚すれば職場全体の信頼を失う原因になります。
また、本人にとっても「その場しのぎ」と受け取られやすく、逆に不信感を抱かれる可能性があります。
待遇改善は一時的な対処ではなく、透明性と公平性を持って行うことが大切です。
家族を巻き込むようなプレッシャー
退職を引き止める際に、家族を巻き込んで説得しようとするのはNG行動です。
「ご家族にも迷惑がかかるよ」などの発言は、相手のプライバシーに踏み込むだけでなく、不適切なプレッシャーとなり強い不信感を招きます。
家庭の事情は本人にとってデリケートな問題であり、第三者を利用するような行為は、関係性の悪化やトラブルの原因になります。
対応はあくまで本人との信頼関係の中で行いましょう。
「辞めたら後悔する」などの精神的圧力
「辞めたら後悔するよ」「次の職場では通用しないかもしれない」など、本人の不安をあおるような言葉で引き止めるのは精神的な圧力となりNGです。
このような対応は、相手の自己判断を否定し、恐怖や罪悪感を植え付けてしまいます。
結果的に信頼関係が壊れ、退職の意思をさらに固める原因にもなります。
引き止めは、否定ではなく理解と尊重の姿勢を持って行うことが大切です。
引き止めが失敗した場合の正しい送り出し方

もし引き止めが成功しなかった場合でも、関係をこじらせず、円満に送り出すことが大切です。
前向きに送り出す
仕事を辞めることが決まっても前向きに送り出してあげましょう。
退職後もそれまで会社で働いてきたことは良い勉強や経験になったはずで、次の会社でも経験を活かし活躍ができるように期待していると送り出しましょう。
転職しても仕事関係で付き合いがあることもあるので、良好な関係は保ちましょう。
無理に引き止めない
仕事を辞めるにしても留まるにしても最終的な決断は本人に委ねて無理やり引き止めないようにしましょう。
無理に引き留めようとすればするほどしつこいと思われてしまい、悪い印象を与え逆効果になってしまいます。
無理に引き止めても仕事を辞める原因が改善されない限り、また辞めることになってしまいます。
退職理由を振り返り、改善につなげる
退職の理由をしっかりとヒアリングし、会社側に改善すべき点がある場合は真摯に受け止め、今後に活かすことが重要です。
待遇や人間関係、働き方など、退職の背景には必ず原因があります。
同じ理由で他の社員が辞めることを防ぐためにも、フィードバックをもとに職場環境の見直しや制度改革を行い、より働きやすい職場を目指す姿勢が求められます。
伝え方で変わる退職の引き止め術
退職を考える社員と真剣に向き合い、信頼関係を築くことは引き止めの大切なポイントです。
しかし、どんなに話を聞いても伝え方がうまくいかないと、相手の本音を引き出せなかったり、気持ちがすれ違ってしまうこともあります。
そんな時には人間関係がうまくいく!伝え方コミュニケーション検定でコミュニケーション力を磨くのがおすすめです。
実践的なスキルを身につけて、職場の人間関係をもっと良くしてみませんか?




